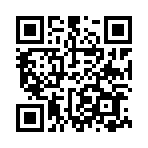2015年05月15日
淡水魚調理に関しての基本姿勢
釣獲した魚の調理記事は、別ブログ
陸・海・空・連(りく・かい・くう・れん)
Trident トライデント
にて掲載しておりますが、今回は淡水魚調理における、私の基本姿勢について書きます。
淡水魚調理に際しての献立の選択は、基本的に東南アジア圏諸国のメニュー若しくはそれに自己流のアレンジを加えてものが多いです。
理由としては、
① 食材とされる淡水魚の生息する水系が熱帯性の土壌のため、濁りが激しいこと、その為に特有の臭気がある。
② 高温多湿の気候条件なので、発汗が激しく、塩分とミネラル分不足に陥りがち、補給手段として高塩分の旨味調味料『魚醤』の活用が発達したが、特有の臭気を持っている。
③ 宗教的戒律、特にヒンドゥー教、イスラム教圏では、牛肉、豚肉は禁忌とされる食材、代わりに山羊肉、羊肉が重用されているが、特有の臭気がある。
④ 食材も高温多湿の気候条件のため、傷みやすく臭気を発しやすい、臭気を消す手段として、香辛料、香草類の利用が発達した。
⑤ 食文化的に主食がコメであり、旨味を重要視する。
素人的見地からも、臭気を消す手段として非常に理解しやすく、実際に調理しやすいですね。
私が、釣獲し、食材に供している魚種は、オイカワ、ウグイ、アブラハヤ、タカハヤ、ヤマメ、イワナ等の渓流、清流域の魚種は少なく、ブラックバス、ライギョ、ブルーギル、マナマズ、フナ類等の止水域の魚種が多いです。実際の調理に関しても、非常に応用しやすいです。
勿論、日本料理、西洋料理にも食材の臭気を消す手段は存在しますが、悲しいかな私の知る限りでは、東南アジア料理程種類がありません。
そんなわけで、過去の調理例は、東南アジア料理が多いですね。
陸・海・空・連(りく・かい・くう・れん)
Trident トライデント
にて掲載しておりますが、今回は淡水魚調理における、私の基本姿勢について書きます。
淡水魚調理に際しての献立の選択は、基本的に東南アジア圏諸国のメニュー若しくはそれに自己流のアレンジを加えてものが多いです。
理由としては、
① 食材とされる淡水魚の生息する水系が熱帯性の土壌のため、濁りが激しいこと、その為に特有の臭気がある。
② 高温多湿の気候条件なので、発汗が激しく、塩分とミネラル分不足に陥りがち、補給手段として高塩分の旨味調味料『魚醤』の活用が発達したが、特有の臭気を持っている。
③ 宗教的戒律、特にヒンドゥー教、イスラム教圏では、牛肉、豚肉は禁忌とされる食材、代わりに山羊肉、羊肉が重用されているが、特有の臭気がある。
④ 食材も高温多湿の気候条件のため、傷みやすく臭気を発しやすい、臭気を消す手段として、香辛料、香草類の利用が発達した。
⑤ 食文化的に主食がコメであり、旨味を重要視する。
素人的見地からも、臭気を消す手段として非常に理解しやすく、実際に調理しやすいですね。
私が、釣獲し、食材に供している魚種は、オイカワ、ウグイ、アブラハヤ、タカハヤ、ヤマメ、イワナ等の渓流、清流域の魚種は少なく、ブラックバス、ライギョ、ブルーギル、マナマズ、フナ類等の止水域の魚種が多いです。実際の調理に関しても、非常に応用しやすいです。
勿論、日本料理、西洋料理にも食材の臭気を消す手段は存在しますが、悲しいかな私の知る限りでは、東南アジア料理程種類がありません。
そんなわけで、過去の調理例は、東南アジア料理が多いですね。
Posted by 鎌海豚 at 18:48│Comments(2)
│研究
この記事へのコメント
日本でも長野、滋賀、群馬とか淡水魚の文化がありますけど、なれ鮨はあっても、魚醤の文化はありませんね。鯉洗いの酢味噌あえ位くらいでしょうか?
Posted by アトランティックな夜 at 2015年05月17日 20:43
>なみ平さん
私自身は、魚醤は、塩辛と表裏一体の文化と考えておりますので・・・・
淡水魚では、アユの名産地で作られている塩辛、『うるか』が該当すると思っております。
岐阜県の長良川、熊本県の球磨川、島根県の高津川、大分県の大野川産等のアユから作られています。
私自身は、魚醤は、塩辛と表裏一体の文化と考えておりますので・・・・
淡水魚では、アユの名産地で作られている塩辛、『うるか』が該当すると思っております。
岐阜県の長良川、熊本県の球磨川、島根県の高津川、大分県の大野川産等のアユから作られています。
Posted by 鎌海豚 at 2015年05月17日 21:25
at 2015年05月17日 21:25
 at 2015年05月17日 21:25
at 2015年05月17日 21:25※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。